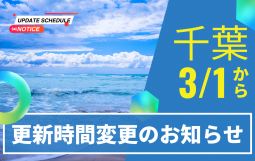明けましておめでとうございます。
新年のご挨拶でご紹介させて頂いた、NPO湘南ビジョン研究所の小冊子に特集されたコラム『サーフィン、ライフセービング、そして波伝説』を、同所のご協力により特別にご紹介させて頂きます。
新しき年の始まりにおいて、皆さまのご健勝とご多幸を衷心よりお祈り申し上げます。
2018年元旦
株式会社サーフレジェンド
(気象庁気象予報業務許可 第70号)
代表取締役 加 藤 道 夫
文/森 休八郎
Photo/Serikawa Ariyoshi
協力/NPO湘南ビジョン研究所
浦賀水道に面した、横須賀・鴨居漁港。
少年が、走っている。一方の手に釣竿を、もう一方で10円玉を握りしめた少年が、走っている――。
それから50年以上の時が過ぎた。かつての少年は、あの頃と同じようなまなざしで、海を見つめていた。
加藤道夫。サーファーにとって今や欠かすことのできない波情報「波伝説」や、釣り人・漁師向けの情報「海快晴」を発信する気象予報会社「サーフレジェンド」の社長である。最初は遊び、そして趣味だった海とのかかわりは、やがて仕事へと結びついていった。いったいどんなきっかけで――。

10円玉を握りしめて
加藤は1957年12月、鴨居に生まれた。海が、漁港がすぐそばだった。幼い加藤少年の興味を引いたのは、釣りだった。加藤は思い出す。
「学校から帰ると毎日のように、安いリールをつけ、冬ならカレイ、それにアイナメなども釣れた。エサはゴカイ。握りしめていた10円玉は、その代金だった。
「毎日のようにエサ屋さんに行くと、そこのおばあさんが売ってくれるんです」
ところがのちになって、ゴカイは10円で買えるものではなく、50円から100円はするものだったことを知る。
「昔お世話になりました、とあいさつに行き、いきさつをお話ししました。そしたら『あー君か』と。毎日のように10円持ってくるものだから、断り切れなかったみたいですね」
漁村だけに、小学校のクラスメートも漁師の息子が多かった。
「友達のおやじが、『道夫、釣れたか?』と聞いてくる。『釣れない』と答えると、魚をポーンとくれたりしました」
小学校3年生まで鴨居で過ごした後、父親の仕事の関係で磯子に転居。海からはやや遠のいた程度だったが、青春時代はバレーボール、そして草野球に熱中した。俊足巧打、そして堅守のセンターだった。
横浜市立金沢高校に通い、なんとなく大学進学を考えていたころ、進められて横浜市役所を受験した。結果は、合格。
「『大学に進んで、4年後市役所を受けても合格するかどうか保証はないぞ』という周囲の声もあり、そのまま就職することにしました」
ところが、当時は高度成長時代で市役所も職員が多数採用されたため、4月と10月に分けての採用となった。加藤は後者となり、高校を卒業してから半年ものブランクがある。
「アルバイトしましたよ。体を使う仕事でしたが、月に15万円は稼いでいました。で、10月に入所してびっくり。市役所の給料は7万7000円でしたから、一気に半減でした」
最初は横浜市金沢区役所に配属され、加藤の社会人人生が始まった。

悔しかった最初の「出会い」
就職後も野球に明け暮れていた、20歳の夏。加藤はその野球仲間が、サーフィンに夢中になっていることを知った。じゃあ自分も連れて行ってもらうか、と、千葉の鴨川に向かった。
「ぼくは水泳も得意だったし、簡単にできるだろうと思っていました」
ところがその日の鴨川の海は風が強く、今から思えば、沖に出るのはかなり困難なコンディションだった。それでも加藤は、体力任せのパドリングで海へと出た。
「20分ほど必死に漕いでも、いっこうに出られないんです。休憩を何度も挟んで挑戦したんですが、無理。結局初サーフィンはボードに立つことはおろか、アウトに出ることもできずに終了でした」
この現実は、加藤のプライドをいたく傷つけた。帰りの車の中ではずっと仏頂面だったことを、今も思い出すという。そして加藤の闘争心に、火がついた。
「もう悔しくて悔しくて、それから辻堂で毎週のように“コソ練”ですよ。当時は磯子に住んでいましたが、そこから真っ赤なワーゲンのビートルで、辻堂に通っていました」

当時市役所の勤務は、日曜は休日、土曜日は半ドン(午前のみ勤務)だった。そうなると、土曜の午後と日曜日しか海に入ることができない。有給休暇をいかにサーフィンのために使うか、ということにも心を砕いた。だが、やる気マンマンでやってきても、海のコンディションがサーフィン向きではなく、空振りに終わることも多かった。
「当時、辻堂に『サーフ&サンズ』というサーフショップがあり、時々顔を出していました。店員の女性はかわいいし、店内にはムスクの匂いがして、湘南らしいとてもおしゃれなお店だったのを覚えています。ちなみにそのお店があったまさにその場所に、今サーフレジェンドがあります。これもご縁なのでしょうね」
その「サーフ&サンズ」が無料で行っていたのが、辻堂の波情報を教えてくれるテレホンサービスだった。毎日11時に更新されるこの情報に耳を傾け、さらに自分でも天気図を見て、海の状況を予測するようにもなった。これがのちの「波伝説」の原点となり、加藤の人生の縦糸を形作ることになる。
「1990年代あたりまでは、サーファーはロン毛が多かったんですよ。ぼくも公務員のくせに長かった。役所の先輩からは『ドイツ軍のヘルメットみたいだな』なんて言われたものでした」
サーファーとして海に入り浸っていた加藤だったが、今度は仕事でも海とかかわることになっていく。
「海の公園」担当に異動
加藤は24歳の時、横浜市港湾局に異動し、横浜市金沢区の「海の公園」担当となった。
「海の公園」は、金沢地先埋立事業の一環として、横浜市が整備したものだ。1980年に人工海浜が暫定的にオープンしたが、さらに海水浴場の開場も計画されていた。
「横浜市は、かつて海水浴場だった浜をどんどん埋め立てていきました。そこでここに人工海浜を造ることで、海岸線を市民にお返しする、という発想がありました」
暫定オープンした砂浜は、たちまち人気スポットになる。というのも、アサリやバカガイ(アオヤギ)が大量に獲れることが知れわたったからだ。ゴールデンウィーク前後には数多くの人が訪れる。管理業務に明け暮れて休日などないに等しく、なんとか平日に休みを取ってその埋め合わせをするほどだった。
「ここの砂浜は、100分の1勾配(100m進むと1m下がる)で造られているんですが、これがアサリにとっては理想的な環境だったみたいです。潮干狩りで有名なところの中には、シーズン前に稚貝を撒いたりしていますが、ここでは一切やっていません」
加藤が忙しかったのには、管理業務以外にも理由があった。それは、海水浴場オープンのための準備作業だった。
「運営ノウハウなど市にはありませんから、何もかもがイチからのスタートでした。ぼくは、特に重要な“ライフセービング”に力を注ぎました」
当時横浜市内では、ライフセービング講習会や水上安全法講習会などは行われていなかった。そこで藤沢市まで行って、海水浴場の監視員に交じって日本赤十字社の水上安全法講習会を受講した。もちろん加藤も受講者のひとりである。それは過酷だが、充実したものだった。

ライフセービングへの目ざめ
1987年7月20日。「海の公園海水浴場」の正式オープンは翌年からだったが、すでに泳ぎ始める子どもたちが少なくなかったため、翌日からの夏休みに備えて、加藤は「海の公園」で、監視員となる学生たちとともに監視タワーの設置など安全対策の準備に没頭していた。
そこに、急報が届いた。砂浜のすぐ近くで子供が溺れた、という。加藤は高校2年生の監視員とともに現場に向かった。
「行くと、売店内の床に小学5年生の男の子が横たわっていました。意識はなかった。知らせを聞いて駆け付けた男の子のお姉さんは、変わり果てた弟の様子を見て泣き叫んでいました。男の子は、亡くなりました」
当時、ライフセーバーを含む一般人への救急救命講習の中には、人工呼吸法はあったが心臓マッサージは「医療行為に該当する」ということで認められていなかった。
「ぼくも、高2の監視員も激しいショックを受けました。それではだめだ、とそれから本格的にライフセービングに関わるようになりました。高2の彼も、以来ずっと監視活動を続けています」
加藤にとっての人生の横糸――ライフセービングとのつながりは、この事故がきっかけで深まった。指導員の資格を取得し、各地で開く講習会ではインストラクターとして後進を指導。また2016年まで4期12年、神奈川県ライフセービング連盟理事長を務めた。だが、
「日本のライフセービングの限界を感じました」
と、加藤は言う。

「日本のライフセービングは、夏の海水浴客のためだけの監視活動で、学生のアルバイトが中心です。一方、海外のハワイ、カリフォルニア、オーストラリアなどでは、マリンスポーツのすべてを見守り、ビーチ全体の安全安心をコントロールする、公務員の『ライフガード』が配置されている。日本のライフセービングの最大の問題は、公務員としての、プロとしての『ライフガード』になれない、ということなんです」
加藤自身が地方公務員だけに、この現実は痛いほど理解できた。が、もし常駐のライフガードがいれば男の子は助かったのではないか、という悔恨の思いもある。

「各大学にライフセービング部があり、その部員は大学時代をそこにつぎ込んで頑張っています。ところが、卒業とともにライフセービングから離れてしまわざるをえない。4年間で得た経験や知識が生かされないのです。もし、職業としての『ライフガード』が確立できれば、彼らにとっても、海で遊ぶ人にとってもいいことなのに、という思いは、今も強くあります」
波情報、発信!

多忙な中でもサーフィンは続けていた、30代半ば。サーフィン雑誌である情報を知った。
「アメリカに『800番』という、日本の『ダイヤルQ2』の原点みたいな電話サービスがあり、その中に、1ドルの有料波情報の提供がある、というんです、これはいいな、と思いました。こういう波情報があったらみんな喜ぶぞ、と」
おりしも、日本でも「ダイヤルQ2」サービスが始まろうとしていた。加藤は、鎌倉・七里ガ浜に住む友人とともに、「七里ガ浜サーフインフォメーション」を立ち上げたのだ。
「売り上げがウェットスーツ代になればいいね、くらいの気持ちで始めました。毎日朝5時と24時に、七里ガ浜の波情報を録音して流しました」
最初は軽い気持ちで始めたものだった。が、運命は転変する。
「ぼくと同い年で同じ月生まれ、しかも双子のようによく似ていると言われ、親友として付き合っていた従兄弟に肺ガンが見つかり、あっけなく亡くなったんです。急に『死』が身近なものになり、人生とははかないものだ、という思いにとらわれました」
役所では、上司から管理職試験を受けるように勧められていた。一方の波情報は、友人が本業に専念せねばならない事情が生まれ、存続が危ぶまれる状況になった。加藤は、考えた。
「サーフィンにこだわっていたし、波情報にもこだわりがあった。妻と子供2人を抱えていたけれど、まだまだ体力はある。“よし波情報をやる!”と決心し、18年勤めた横浜市役所を辞めて、有限会社を設立し、波情報に専念することにしました」
七里ガ浜から湯河原までの10のポイントを1日2回往復し、自分の目で海のコンディションを確かめる。さらに気象予報会社から直接情報を買い、その2つを合わせて、独自の情報を発信する。これが人気を呼び、情報エリアもどんどん拡大していった。
海の安心安全を
その後、FAXによる配信、1999年から始まったNTTドコモの携帯電話サービス「iモード」での情報発信、さらにスマホ時代の到来で、アプリを利用したサービスの提供と、メディアの変遷に合わせて発信形態を変えてきた。
その間、京都大学防災研究所と産学共同研究を行い、独自の波浪予測システム「Wave Hunter」を開発して特許を取得。「波伝説」と「海快晴」の情報は、さらに精度を高めている。今後は、アジアにまでエリアを広げたいともくろむ。
もちろんここまで順風満帆だったわけではない。パートナーを組んでいた会社との関係を解消せざるを得なかった時には、17万人いた有料会員がゼロになる、という地獄も覗いている。
それでも加藤がめげないのは、「海の安心安全」に対する執念があるからだ。加藤にとっての“縦糸”である波情報は一見、サーファーに「いい波」を教えることのように思えるが、裏を返せば、危険情報を届けることでサーファーの安全を守っているものでもある。
そして、「ライフガード」のプロ化という“横糸”も、加藤の胸中にずっとある。
「オリンピックを起爆剤に、日本はさらなる外国人観光客の誘致に力を入れていますが、日本の海は、充分に観光の売りになると、ぼくは思っています。湘南を見てください。海でサーフィンやマリンスポーツを楽しみ、鎌倉で日本の文化に触れ、箱根で温泉を満喫する。これが湘南のよさだと思います。が、そのためには、プロの『ライフガード』が、どうしても必要なんです」
12月に還暦を迎えた加藤。だがその若々しいエネルギーが衰えることはない。少年の日と同じように、加藤は今も、走っている。