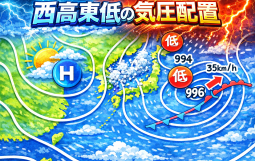皆さん、こんにちは。
雨が降ればジメジメし、晴れれば暑さが体にこたえる季節になってきましたね。
日本の伝統的な暦における6月の月の名前を水無月(みなづき)といいますが、梅雨の時期なのに何で水の無い月なのか疑問に思ったことがある方も多いと思います。
僕も最近、カレンダーを見て不思議に思ったのですが、「無・な」が「の」という意味の連帯助詞だから、水の月ということになるそうです。
また、同じ「無」が入っている旧暦10月を神無月(かんなづき)といいますが、こちらは全国の八百万の神々が出雲に集まり、神が不在となるために神の無い月ということになり、出雲では神在月というのが一般的な説です。
ただし、水無月と同じように「無・な」が「の」という意味となり、神の月という説もあるそうです。

昔の言葉の意味を理解するのは難しく、間違って解釈していることも多いかもしれませんが、昔のほうが科学的根拠が乏しく、謎が溢れていたと思うので、どの説でも通じるような気もします。
波チェックでは雨が降るとスマホの操作のことなどで普段より大変になりますが、梅雨が終わって猛烈な暑さになると、それはそれでハードになります。
水の月でも、水の無い月でもどちらでもいいような気になってしまいます・・・。