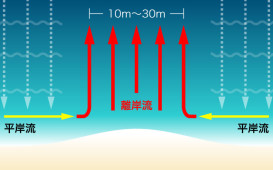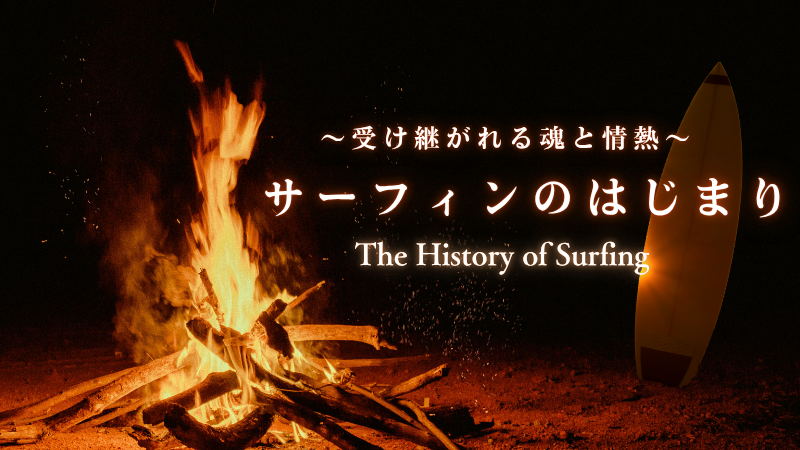
何百年も前、南太平洋の島々。
それは、古代ポリネシア民族の生活様式から始まります。
彼らは「海の民」と呼ばれ、大航海時代よりもはるか以前から高度な航海技術を持ち、大洋を渡っていました。
片側に浮きをつけて転覆しにくくしたアウトリガーカヌーと飛ばれるカヌーで、珊瑚礁の外に漁に出かける日々。
毎日のように波が押し寄せる珊瑚礁の海で、漁の帰りには自然と波に乗って帰路につくようになったのがサーフィン誕生の始まりと考えられています。
こうした波乗りの技術が、やがて漁業の一部としてだけでなく、楽しみとして独り歩きを始めます。
カヌーが次第に小型化し、オロやアライアと呼ばれるサーフボードの原型が生まれ、透き通ったターコイズブルーの海で、古代ポリネシアの人々は丸太や削った木の板で波と一体になっていました。
サーフィンは神への敬意と、海とひとつになる儀式でもありました。
やがて、王族だけが乗ることを許された特別な長い板など、形状の異なる板も続々登場します。
18世紀、イギリスの探検家ジェームス・クック船長がハワイに上陸し、ヨーロッパ人として初めてサーフィンを目撃。
航海日誌には、サーフィンを楽しむハワイアンの様子が詳しく書き記されています。
しかし皮肉にも、彼の発見によってヨーロッパの宗教が押し寄せ、布教の妨げになるとしてサーフィンは禁止されてしまいます。
これにより、一時的にその文化は衰退。
良い波の日に、誰も教会に来なくなってしまうことも一因だったとか。
時を経て20世紀初頭、教会の反対もありましたが、ワイキキの海岸だけは黙認されると、ハワイアンだけでなく移住者たちもサーフィンを楽しむようになりました。
そして、ひとりの水泳選手がこの楽園の遊びを世界に広めます。
それが、のちに功績を称えられハワイとオーストラリアでブロンズ像が建てられる、「近代サーフィンの父」デューク・カハナモク。

彼はオリンピック金メダリストであり、生粋のウォーターマン。
水泳大会で世界中を旅する中、どこへでもサーフボードを持って行き、現地の人々に波乗りの楽しさを伝えました。
1914年、オーストラリア・シドニーの海でデュークが魅せたライディングは、まさに衝撃。
その日から、南半球の人々も波に魅せられていきました。
日本においては1960年代、湘南や千葉の海で駐留アメリカ人がサーフィンを楽しむ姿を見た地元の少年たちの憧れから広がりました。
自作の「フロート」と呼ばれるボードで模倣し、1965年には日本サーフィン連盟が設立されます。
翌年には全国大会が開催されるなど、サーフィン文化は着実に根付き、今に至ります。

海とサーフィンを愛する心は、世代や国境を超え、サーフボードやサーフギアも進化を続けています。
次に乗るその1本の波は、何百年もの歴史と、海を愛した無数の人々の想いと繋がっています。
サーフィンの歴史を振り返ると、次のライディングはいつもと違って見えるかもしれません。
さあ、今度の週末は海へ――。
あなたの一本が、また新しい物語を紡ぎます。