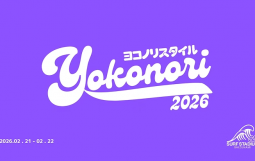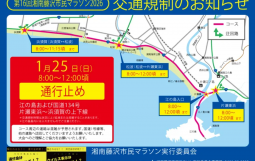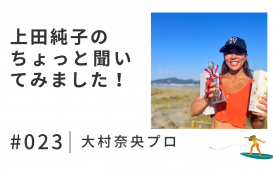ビッグウェーバーであるラモン・ナバロ氏の、チリ・プンタデロボスの環境を守る活動とそのスピリッツを描いたショートムービー『ザ・フィッシャーマンズサン』(2015年;クリス・マロイ監督;パタゴニア制作)は、世界中から高い評価を受けました。
そのラモン・ナバロ氏が来日し、パタゴニアストア東京では2月8日(金)に、パタゴニア大阪では2月10日(日)にスライド&トークショーが開催されました。波伝説では、昨年フィジー・クラウドブレイクのヒュージサイズでの伝説的なライディングを成功させた時のことを含めて、単独インタビューをさせて頂きました。

今回の来日の目的について
2つあります。
1つ目は、昨年のクラウドブレイクでのライディングのトークショーが東京と大阪であるためです。
2つ目は、今ドキュメンタリーフィルムを制作しているので、それを兼ねての来日となりました。
2015年に『ザ・フィッシャーマンズサン』が公開されて大きな反響がありましたが、それからご自身にとって何か変わったことはありますか?
『ザ・フィッシャーマンズサン』が公開されたことは、チリにとって非常に画期的な出来事でした。
プンタデロボスを守るプロジェクトが始まり、実際に保護区とすることができ、そのプロジェクトは完了しました。
最初は住民が自分たちであまりお金をつぎ込まなくても成し遂げられるという信念がなかったので、このプロジェクトにコミュニティーから信頼を得られませんでした。しかし、何とかプロジェクトを成し遂げることができたので、最終的には周りからの信頼を得ることができました。
目に見える成果を上げることができたので、このプロジェクトが機能していたのだと分かり、周りの人たちの自信にもつながりました。
我々の活動は、ピチレム周辺から始まった小さな活動でしたが、そこから沿岸部全体に広がり、今ではチリ中の商業施設で、『プラスティックの袋をお客さまに出してはいけない』という法律ができました。
もしお客さまにプラスティックの袋を出してしまうと、お店が罰せられます。法令化されたことにより、みんなの自信にもなりました。
余りにも反響が大きくなったので、昨年実際に大統領がプンタデロボスにいらして、その時に大統領から直々に指名されて、環境保護の重要性について皆の前でお話をする機会を頂きました。
現在の活動はどのようなことをされていますか?
保護活動の第一段階である『保護地域の土地購入』に進んでいます。
そのために、『この地域を守る』財団法人を設立しました。
その財団によって、プンタデロボスにカルチャーセンターを作ろうと思っています。そこにNGOなどを招いて環境保護活動に関するお話をしてもらったり、沿岸部の植生が破壊されてきているので、まず温室を作り、昔からの植物を育てて、その苗を沿岸部に植えられるようにしていく段階に入っています。
さらに今は、波がブレイクするポイントの「波の保護」に向けて法令化していく活動も進んでいます。
小さいプロジェクトから始まりましたが、現在はこの活動に係わっているNGOがいくつもあります。
こうした実績が大きな反響を呼び、「実際に何か活動すれば成果が見える」「自分たちの力で動かすことができる」ということが分かり、サーファーだけでなく、地域のみんなが参加してくれるようになりました。
もちろんパタゴニアさんからの支援もいただいています。
パタゴニアさんは、この活動に限らず、チリ全体の環境保護も理解し、支援して頂いているのでとても助かっています。

2018年、クラウドブレイクで歴史に残るビッグウェーブをメイクしたとき、とてつもない大きな波に向かうためにどのように精神統一しましたか?また、メイクした後の気持ちは?
誰しもどこかに行くときや、大会に向かう時は期待を抱いてそれなりの準備をすると思います。
私が最初にフィジーに行ったのは2012年の時でした。フィジーはプンタデロボスと同じレフトの波ですし、今まで行った外国の中でもとても居心地の良い環境でした。
その時も2本の非常に良い波に乗ることができましたが、「パドルインでは無理だろう」という波でした。
今回もそういう波を求めて、「あの時の2本の波」を見つけるためだけに向かいました。
2012年の時のような波に乗りたいと思うのですから、もちろん準備は周到に行いました。
トレーニングもちゃんとしました。しかし、実際に波に立ち向かってみると、精神統一とかではなく自然と身体が動くものでした。
2012年の時の想いが少しフラッシュバックしましたが、あとは普通に乗ることができました。
その日ホテルに戻って、「きょうの波はどうだったか」と思い返してみましたが、非常に疲れていて、自分がどんな事をしたのか実感がありませんでした。ですが、電話は鳴りっぱなしだし、SNSではかなり盛り上がっているし、自分がしたことがとても凄いことだったのだと、後からじわじわと実感がこみあげてきました。
それでも、自分が成し遂げたことの大きさを信じることがなかなか難しかったです。
2012年から6年ぶりにクラウドブレイクにビッグウェーブが到達する予想が出た時、どんなことを思いましたか?
6年間という期間が空きましたが、フィジーは私にとってとても居心地の良い好きな場所なので、あの時のような良い波に乗りたいという気持ちでずっとイメージトレーニングをしていました。
ただ、それだけ大きな波に乗るという事は何が起きてもおかしくないので、安全対策を万全にするための準備に翻弄され、あまり考える余裕はありませんでした。
例えば物理的な面では、酸素やライフジャケット、ボートで待機してもらうドクターの手配などの準備です。
肉体的な面では、到着するまでの1週間は野菜しか食べないデトックスを行いました。また、それを通じて精神的な面でも統一を図ろうとしました。
よって、物理的、肉体的、かつ精神的な面の準備に忙しくて、何かを考える時間はありませんでした。
途中でトーインにアクシデントがあったかと思いますが、その時に動揺はしませんでしたか?
そうなんです。ビスが3本取れていたんです。
その日は風が強かったのですが、朝早くに、コール(クリステンセン)から、ジェットスキーもサーフボードもすべて用意をするから、今から一緒に行こうよ~と誘われました。
トーインが久しぶりだったので、1本目の波はお試しという感じで小さめの波に乗ったのですが、乗ったら『なんかおかしいな……!?』と思い、ライディングを終えてサーフボードと足を固定するストラップを見たら、ビスが3本も取れていたんです。途中でストラップが外れず、本当にラッキーでした。
もしまた、クラウドブレイクに同じような波が来るとわかったら挑戦しますか?
もちろん挑戦しますよ!!

ラモン氏にとって日本はどんなイメージがありますか?
2015年にも来日しましたが、その時は映画の紹介のための来日で、すごい忙しくてサーフィンができたのは2日間だけでした。
今回はまだ到着したばかりなので、日本のポイントのことはよく分かりませんが、実は私は大都市がすごく苦手なんです。
なので、今回もどうしようかと思っていましたが、前回サーフィンをしに行った町がとてもよかったのです。ほとんどが低い建物で、大都市とは違う感じでとても安心しました。
そして驚いたのが日本の人たちの謙虚さです。
他の人たちへの敬意の示し方がとても素晴らしく、とても感銘を受けました。例えば、ゴミを拾う人たちの姿、パンを売る人、銀行の窓口の方の接客の仕方など、世界の人たちがみんな日本人みたいに謙虚になって、他の人に対して敬意を払ってくれたら、「世界はもっと良くなるんだろうなぁ~」と思いました。
そういう面で、私は日本に来てとても感動しました。
また、日本のサーファー、日本の波はどうですか?
波についてはビデオで見ているぐらいなのですが、小さい波を皆さんとてもうまく乗りこなしていますよね。
ハワイでは「ワキタピーク」という名前が付くぐらい脇田貴之さんは有名な方です。また、とてもアグレッシブな感じでライディングする若い世代が出てきていると思います。そういう意味では、世界的にも日本のサーファーは敬意を払われていると思います。
日本の小波ではビッグウェーバーとしては物足りないですか??
そんなことはないですよ。
たしかに若いときは「皆に見せたい」という気持ちがあったので、大きな波を探していましたが、今は立場を確立することができたので、1ftとかでもいいんです。
自分の業績とかよりも、いろいろな波をさまざまな板を使って楽しみたいという気持ちになってきました。

いよいよ来年、2020年にサーフィンがオリンピック競技として開催されますが、ビッグウェーバーであるラモン氏の観点ではいかがですか?
正直に言うと複雑な気持ちはあります。
コンテストの開催される日がどのくらいのサイズになるのか分からないし、その日の波を誰かがつかみ、それだけで順位をつけねばならないということです。
サーフィンと言う神秘的な部分を、それでは測れないかなと思います。
ただし、オリンピック競技となり、新しい世代の人たちがこれでいろいろな形での支援を受けられるようになったり、サーフィンが世界の人たちにスポーツとして認知される良い機会になるとも思います。そういう意味ではメリットがあると思っています。
今回は日本なので良かったのですが、今後のホスト国に海が無かった場合や海があっても波が無かったらどうするのか心配です。

ナバロ氏とパタゴニアサーフ東京スタッフと木下デヴィッド氏
エディ・アイカウへの招待選手となっていますが、ラモン氏にとってエディへの想いは?
ハワイ・ワイメアでエディについての話を聞きましたが、自分がプロとして活動するには、こういう世界に身を置くことになるんだと思いました。
自分がプロサーファーとして目指すトップのキャリアというのは、彼のような存在であり、海の近くに住んで、派手な暮らしをするのではなく謙虚で、家族と一緒に暮らす生き方こそが素敵だと思いました。私にとっては、目指すべきものが見えたきっかけになりました。