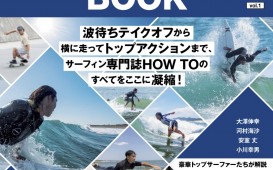ピックアップ・コンテンツ
In The Pink
「ピンクに染まって」
ピーター・タウンネンドは、生涯輝きつづける人生を送っている
文:フィル・ジャラット
ポートレート:ショーン・デュフレーヌ
ピンクのシャツに身をつつんだずんぐりむっくりの男。いかしたスニーカーを履(は)き、しっかりした足取りで群衆をかきわけ進むその姿は、さながら田舎の政治家が選挙遊説にのぞむ雰囲気を醸(かも)しだしている。つねに笑顔であっちにシャカし、こっちに握手し、群衆のなかをスマートに練り歩く。PTは、忙しそうにその会場にいる人たちとあいさつを交わしていた。彼がプロサーフィンの初代チャンピオンになってから約40年、いや、そのもっと前から彼はずっとこれをやっているのだ。彼は、その文化と歴史が築きあげてきたヒーローにヒール、勝者と敗者、貧しい者から億万長者まで、分け隔てなくこのスポーツのためにできるかぎりを尽くしてきた。

Return To Kamchatka
「カムチャッカ再訪」
ロシア最東端の地で遭遇したヒグマと密漁者と軍警察
文:サイラス・サットン
写真:ディラン・ゴードン
旧ソ連製のヘリコプターで雪に覆われたいくつもの岩の峰を越えると、眼下に大きな湾が広がった。3年近くグーグルアースとにらめっこしてきた目当ての波は、この湾のいちばん奥にある。旅のメンバーは、ガールフレンドのアンナ・アーゴットとカムチャッカで最初のサーファーとなったアントン・モロゾフ、それにぼくが親しくしているカリフォルニア州ベンチュラに住むフォトグラファーのディラン・ゴードンだ。河口周辺をゆっくり旋回するヘリから見下ろすと、深い森林に覆われた崖の下で一見パーフェクトな波がアシカの群れに割って入るようにブレークしていた。前回目撃したサメは、すくなくとも今は見当たらない。

Beach House For All Seasons
「終わりなき夏のビーチハウス」
21世紀の湘南に生まれた、サーファーによるサーファーのための空間、”surfers(サーファーズ)“という名前のビーチハウス。
文:森下茂男
海の家というのは日本のビーチカルチャーだが、時代の流れのなかで海水浴客のニーズによって変貌し進化していく。昭和から平成へ、海の家は家族連れがくつろぐスタイルから、若者たちが音楽を聴きお酒を楽しめるカフェバー・スタイルへと変化していく。こうした流れのなか、2009年にサーファーズという、サーファーたちの手による海の家が逗子海岸に登場する。それはサーファーの持つビーチカルチャーと日本独自の海文化が融合したものなのだろう。サーファーズが誕生する際にマスターピースとなったライブハウスがある。それが1999年に金沢文庫の国道16号線沿いにオープンしたロード&スカイというお店だった。

Portfolio: Tatsuo Takei
ポートフォリオ:竹井達夫
「20年前の生き方」
時代を逆行させるセンチュリー650mmレンズのむこうにみるモダン・ノスタルジア
文:デボン・ハワード
43歳の竹井達男の生き方を決める大きなきっかけとなったのは、ジョン・ミリアスの映画『ビッグ・ウェンズデー』だった。1989年にマットとジャックとリロイの世界を垣間見てしまったこの日本人は、ミリアスが描いた‘60年代カリフォルニアのライフスタイルを追求することにしたのだが、彼をとくに魅了したのは彼らが使っていた道具だった。その色彩とデザインの美学、そしてそれが水の上を動く様子。エンドロールを見ながら彼は、この場所をみつけ、このボードに乗ってみたいという切なる願いを抱いた。

ほかにも、ショートボード革命は1968年にプエルトリコで開催されたワールド・サーフィン・チャンピオンシップからはじまったというナット・ヤングの文章で綴られたその舞台裏のストーリー。そして、貧困とドラッグにはまる南アフリカ、ダーバンのストリートチルドレンをサーフィンによって更生させる取り組みなど、今号もストーリー満載のザ・サーファーズ・ジャーナルをお楽しみください。