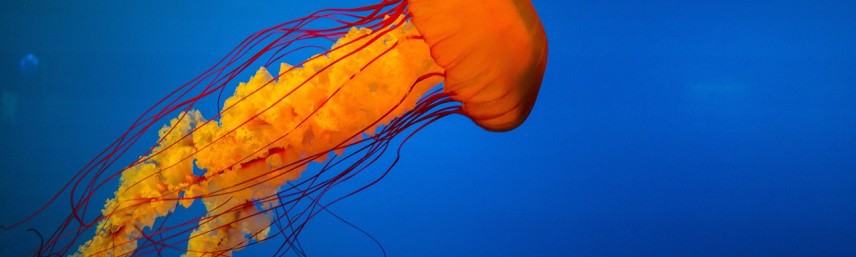
カツオノエボシ
本州以南の沿岸部に生息。8~10月ころ、風に吹かれて沿岸部に近づく。10センチメートルくらいの青い気泡体で海面に浮く。主触手は10メートルもあり、海中に浮遊しており気づきづらい。
- 【症状】
- 主触手の刺胞毒は強力で、刺されるとしびれるような痛みを感じ、後にミミズ腫れができ、頭痛、嘔吐(おうと)、呼吸困難、ショック症状に陥ることもある。
- 【応急手当】
- 最初に海水で触手を洗い流す。流れない時は、刺胞を刺激しないようにゴム手袋をしてから静かにつまんで取り除く(ピンセットなどを使用してもよい)。
受傷部位を“氷のう”で冷やし、安静にする。もし、ショック症状が現れた場合は、ただちに医療機関に受診(搬送)する。
※真水で触手を洗い流すことは、浸透圧の関係で、かえって毒を散布する結果を招くこともあるので避けることが望ましい。
赤クラゲ
沖縄から北海道までの全域に生息。春から初夏にかけて沿岸部に漂着する。10センチメートルくらいの傘に16本の褐色の放射模様があり、40本の触手のうち4本が特に長い。
- 【症状】
- すべての触手に刺胞があり、毒性は強い。刺されると激しい痛みと炎症を起こす。
- 【応急手当】
- カツオノエボシと同様の手当を行う。
アンドンクラゲ
沖縄から北海道までの全域に生息。8~9月にかけて沿岸に漂着する。日中は水中深くに沈み、夕方や早朝、または曇天の日に水面近くまで浮き上がってくる。3センチメートルくらいの立方形の傘と四隅から6センチメートルくらいの4本の触手がある、小型のクラゲ。
- 【症状】
- カツオノエボシと同様の症状がある。
- 【応急手当】
- カツオノエボシと同様の手当を行う。
ハブクラゲ
沖縄だけに生息。夏場の沖縄周辺に出現する。10~12センチメートルくらいの立方形の傘を持ち、四隅から数本ずつ1メートルくらいの触手がある。浮遊力があり泳ぐ。満潮時に多く見られ、ビーチの浅瀬に群れで移動していることもある。
- 【症状】
- 毒性は強く刺され瞬間、焼け付くような痛みを感じる。刺された部分にミミズ腫れが生じ、6時間ほどで炎症性の浮腫をともなった水疱(すいほう)ができる。受傷直後にショック症状を起こし、呼吸停止、心停止に至る場合がある。体力のない方(子供など)が広範囲に刺されると、生命の危険性が特に高い。
- 【応急手当】
- ただちに海からあがり、刺された部位に酢をかける。酢は多ければ多いほど望ましく、30秒程度かけ続けると良い。ただし、その場に酢の用意がない場合は、海水で触手を完全に洗い流す。触手が完全に取り除かれてから、痛みがなくなるまで受傷部位を冷やし続け、ただちに医療機関に受診(搬送)する。
アカエイ
中部より南の日本全域と東シナ海に分布。最大全長1メートルくらいで、浅海からやや深いところの砂底でなかば砂に埋もれて隠れている事が多い。春から夏にかけては、内湾や浅瀬の砂地にきて胎児を産み、冬場に深いところに移動する。
- 【症状】
- 尾部には、長くてノコギリ状の鋭いトゲがあり、このトゲを覆う皮膚に毒腺がある。深い傷と激しい痛みが長時間続く。傷口周辺は赤紫色に腫れあがり、水疱(すいほう)を生じる。重傷になると血圧降下、下痢、発汗、呼吸障害を起こし、死に至る場合もある。
- 【応急手当】
- トゲを注意深く取り除き、受傷部位を40~45度のお湯に60~90分くらいつけると痛みが和らぐ。
※受傷部位をお湯につけるか、お湯の入ったビニール袋を当てる。どちらもお湯の状態(ぬる過ぎ、熱過ぎ)に注意する。
医療機関へ受診(搬送)する。