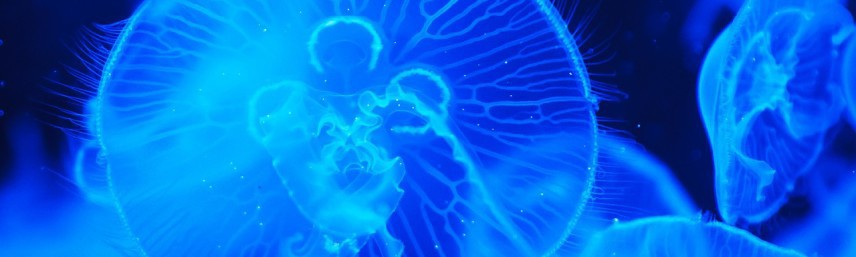
危険な海洋生物-くらげ
海水浴やサーフィンなどをしているときに、海の中で、素肌にチクッとした痛みを感じることを体験された人は多いのではないでしょうか。
ひどい場合には、後から強烈な痛みを感じたり刺された直後から、ミミズ腫れになって患部の周囲が赤く腫れ痛み続けることがあります。
そんな時は、たいていの場合「クラゲ」の仕業と考えられます!
「クラゲ」について……
クラゲは、わたしたち人類が誕生するはるか太古より地球上に生物が誕生して間もない頃から存在する単細胞生物です。
数億年の間、そのカタチをほとんど変えずに海中で生活をしています。
漢字では「海月」または「水母」英語では「Jellyfish」と書きます。
「クラゲ」の特徴について……
ひとくちに「クラゲ」と言っても生物学上は大きく2つに分類され、触手という毒のある刺胞(しほう)という組織をもつ刺胞動物と、刺胞を持たないといわれる有櫛動物(ゆうしつどうぶつ)とがあります。
さらにそれらはたくさんの種類が確認されています。
クラゲの種類
⇒Vol.22 クラゲの種類 をご参照ください。
風や潮流に流されて移動すると思われることから、一般的には夏の終わりに多く発生すると言われているようなのですが、春先に大量に発生することもあり、必ずしも夏の終わりとは言えず定かではありません。
どこで発生し、どのように育ち、どのような環境で生活をしているかは、種類によっても違いがあり、その生態はまだまだ謎に包まれているところが多いのです。
また、すべてのクラゲが人間に危害を加えるわけではありません。
もっとも知られているクラゲは、透明無色で円盤状の「ミズクラゲ」でしょう。
ヌルヌルとした触感がありゼリー状です。大量に発生して工場や発電所などの冷却水の取水口につまってしまうという現象を起こす他は、特に無害と思われていますが、触手をむやみに触ることは勧められません。
ミズクラゲの生体はほとんどが水分で構成されています。
刺胞動物であるクラゲのほとんどが、小さな餌(プランクトンなど)を捕らえるために(種類によって形状の違いがあるものの)糸状に伸びる “触手(しょくしゅ)”をもち、その触手に無数の”刺胞(しほう)”という袋状の組織(数百~数千という刺胞を持つもの)があります。刺胞は肉眼では確認できないほど小さいのですが、何かに触れるとその中にある刺糸(さしいと)と呼ばれる毒針が発射されて突き刺さり、毒液を注入する仕組みになっています。人間に対して強力な毒性を示すものは数十種に過ぎません。
ミズクラゲのように人間には毒性の弱いとされているものもありますが、毒性の強いと思われるものの代表的なものが、カツオノエボシ、アカクラゲ、アンドンクラゲ、カギノテクラゲ、ハブクラゲなどです。
クラゲの生体からちぎれて離れ、水中を浮遊している触手であっても皮膚に触れることで同じ症状となります。
また、波打ち際などに打ち上げられていても触れないようにしましょう。
症状
種類によって少し違いがある場合もありますが、おおむね以下のような症状です。
・触れた直後にしびれるような激しい痛みを感じ、シビレがともなうこともあります。
・触手が触れた肌の部分を中心にして、赤く腫れます。
(肌に触れた際の状況により、ミミズ腫れになったり赤い発疹(はっしん)がポツポツとできたりします。)
・ひどい場合には、血圧や呼吸の変化、頭痛、吐き気、失神など全身の状態が悪化することもあります。
応急手当
一部の種類を除きほぼ同じ応急手当でよいでしょう。
水中で痛みを感じた場合はクラゲの姿が見えないケースもありますが、どんなクラゲなのかが解れば確認をします。
・まずは患部に触手が付着していればを海水でよく洗い流し、触手を取り除きそれ以上刺胞から刺糸が出るのを防ぎます。
★ 「ハブクラゲ」に刺された場合のみ
酢(酢酸)を患部に吹きかけることで、触手の刺胞から刺糸が飛び出さないようにする効果があることが解っています。(他の種類のクラゲの場合には逆効果になることがあるので注意が必要です。)
・患部の痛みや腫れへの対処
氷水を入れた氷嚢(ひょうのう)などで患部全体を冷やします。
・全身の状態が悪化したり、ひどい発熱、痛みや腫れがひどい場合には、すぐに医療機関を受診するようにしてください。
注意する点
・ビリビリと刺されたと思ったら、絶対にかいたりこすったりしてはいけません。かいたりこすったりすることで、刺胞から刺糸が皮膚に刺さり患部の範囲が広がって痛みや腫れがひどくなってしまいます。
・触手を洗い流す際には、必ず海水を用います。水道水やその他の液体、薬品などを使用することが刺激となって、刺胞から刺糸が飛び出て症状をひどくさせてしまうことがあります。
・手当や触手を取り除く際には、素手で触ってはいけません。
(ビニール袋やゴム手袋などを使って取り除きます。)
・波打ち際に打ち上がったクラゲでも素手では触ってはいけません。
予防
次のことに注意して未然に防ぎましょう。
・ 水中ではウェットスーツやラッシュガードなどを着用し、肌の露出を少なくします。
・ 肌が露出している部分にはワセリンなどを塗っておきます。
・ クラゲを見かけたらできるだけ海に入るのを止めます。
クラゲの毒について
人間に危害を加える強い毒性をもつ刺胞動物類(クラゲ、イソギンチャク、サンゴほか)の毒素については「タンパク質毒素」であるということが示されているものの、化学的に明らかにされているのはまだほんの一部でしかありませんが、毒の成分や強さなどの詳細については研究者からの報告が少しずつされています。まだまだ解っていないことが多いのですが、研究は進んでおりこれからさらに解明が進んでいくことでしょう。